※この記事は医療者が読むことを念頭に作成しています。実際に行うときなど、必ず論文などを確認してから行って下さい。また、2025年7月現在で調べた内容で記載しています。
【要約】
Personalized Pain Goal(PPG)は疼痛治療における個別の目標です。
その特徴としては、PPGの中央値がどの報告でもほぼ同じであり、疼痛治療をおこなっているときのフォロー期間中も変化しにくい、達成した後に追加治療を希望する方も少ないという特徴もあります。
私見ではあるが、従来のclinical Responsとは異なるメリットを持ち、疼痛コントロールのとりあえずの目標値を定めるにはよい指標だと思います。
Personalized Pain Goal(PPG)ってご存知でしょうか?簡単に言うと個別化した疼痛治療の目標値になります。
疼痛は客観的な評価が難しく、その評価も課題の一つだと思います。
疼痛の評価は様々なものが存在しますが、その中でよく使われる指標にNumeric Rating Scale(NRS)があります。これは疼痛を数字に表して評価されるもので私もよく使用しますが、二人の人が同じNRSをおっしゃってても本当に同じ強度の疼痛なのか悩むときがあります。これは私だけではないはず⋯⋯
なので、その疼痛の目標値を本人に考えてもらうということはいい方法だと思います。
ちなみに、Personalized symptom Goal(PPG)もありますが、それはまたの機会に……
Personalized Pain Goalとは・・・
上記で示した通り、PPGは患者自身に疼痛コントロールのとりあえずの目標値を定めていただくもの。最初の1報というのは明確にはわかりませんが、少なくとも2012年のCancerの報告がありますので、その時期には研究されています。
このPPGは、達成した後も、その疼痛強度でよいか再度確認することも必要なんだと思います。
まぁ、それが必要であればということはありますが⋯⋯
それについては後ほど。
PPGの使用方法は⋯⋯
PPGは患者に許容される最大の疼痛の強さを確認するもの。その評価方法はNRS(Numeric Rating Scale)を応用して行われます。
NRSとは⋯⋯
NRSは疼痛では患者の痛みを0〜10までの11段階で評価する方法で、痛みがない状態を0、一番最悪の痛みを10として現在の疼痛を点数で確認する方法。ちなみに私は、0は「痛みがない状態」・10は「想像できる最も強い痛み」として確認しています。
PPGではこのNRSを使って、いくつくらいの疼痛ならば、目標として良いかを確認していく方法。
このような指標であると、この目標値を定めるための質問が重要。
研究によって細かいニュアンス、含める疼痛の種類が異なりますが、海外の論文ではどの程度の疼痛ならば「comfort」であるかどうかを問うことは、調べた報告において共通でした。
日本語では、資料や勉強会を見てみると、「どの程度の痛みなら穏やかに過ごすことができるか?」といった質問で問うことが多いようです。
ここからは私見(なので、読み流して良いのですが)ですが、海外の報告をそのまま日本に当てはめて良いかは疑問があるとは思います。
それは、言葉のニュアンスや国民性(我慢するとか、低めに設定されるとか・・・)の違いが、影響を与えることは十分にあり得ることです。それは、「comfort」と「穏やか」が同じニュアンスになるのかということが一つ、またその国民性が影響を与えるかということも考える必要があると考えています。
なので、海外のデータは参考程度にとどめ、日本で取られたデータを見ていくことが重要だと考えています。ニュアンスにしても、国民性にしても、日本におけるPPGの質問内容で日本でのデータを見ていけば、海外の報告とは少し異なっていても、日本におけるPPGが作られると考えています。
(そういう意味でも日本のPPGを理解するためには、Yuki Sumazaki Watanabe先生の報告は重要だと考えています。)
PPGの特徴
確認できた論文から共通点としては下記の3つ。それ以外にも、PPG未達成の予測要因2)や疼痛による生活への影響3)を検討したものもあります。
PPGの中央値がほぼ同一
どの報告でも中央値はNRS=2〜3程度であることは共通。これは痛みの強度が強い症例から弱い症例まで幅広く試験されていますが、疼痛の強度によらず同様の結果となっています。
ただ、日本の報告ではPPG=0 or 1 を設定される方が多かったように見えました。ただ、日本での報告が少ないのでなんとも言えないとは思います。
ただ、言葉のニュアンスや国民性で傾向は多少異なることは十分に考えられ、海外に比べ日本ではPPGが低く設定される可能性を考慮したほうが良いかもしれませんし、今後の研究でも注目して見てみたいと思います。
Follow up で変更しない事が多い
どの報告でも鎮痛療法を行った後のフォローアップ期間でも、PPGが変化することは少ないとあります。報告を見てみると、大きな変化となった症例は少ないように見受けられます。
Clinical Responseとの比較は・・・
どの研究もClinical Responseとの比較を行っています。Clinical Responseの定義は「 治療前から2ポイント以上の低下、または30%以上の低下」であり、従来から使われる鎮痛効果の基準の一つです。臨床試験などでよく見かけると思います。
どの報告も疼痛を3段階(mild pain、 moderate pain、 severe pain)に分けて、それぞれ検討しています。
共通しているのは、疼痛が強いとPPGは達成しにくく、clinical responseは達成しやすい。それに比べて、疼痛が弱いとPPGを達成しやすく、clinical responseは達成しにくいという関係を記しています。
それぞれの疼痛強度で感度・特異度も計算していますので、気になる方は見てみていただけるといいと思います。
そもそも、NRS9→NRS7に変化がしたらclinical responseは達成していますが、疼痛コントロール良好となるかといえば、そうとは言えないことが予想されます。薬剤の奏功としての評価はclinical resposeで良いが、疼痛コントロールの目標としてはPPGというように使い分けるのがいいのではないかと思います。
PPGの良さは・・・
PPGを達成した後、追加の鎮痛治療を必要とする割合が低かったことが一つのメリットになると思います。
もともと疼痛は主観的な感覚なので、同じNRSでもどの程度不快かは異なることが考えられます。ですが、その個人差に対応して疼痛管理のゴールを設定することができると考えました。
また、従来のClinical Responseは鎮痛療法の有効性を示すのに多く使用されていましたが、それととりあえずの目標となるPPGとは意味合いが異なると思います。
ぜひ、日本での臨床試験の論文を読んでみて下さい。
参考論文4)は日本における論文ですので、日本で行う際には参考になると思います。
総説としては参考論文3)のJCOの論文、日本語での質問の文言では参考文献5)に記載がありますので、確認してみてください。
![]()
参考文献
1)Shalini Dalal, David Hui, Linh Nguyen, Ray Chacko, Cheryl Scott, Lynn Roberts, Eduardo Bruera, Achievement of personalized pain goal (PPG) in cancer patients referred to a Supportive Care Clinic at a comprehensive cancer center Cancer. 2012; 118(15): 3869–3877.
2)Joseph Arthur, Kimberson Tanco, Minjeong Park, Ali Haider, Courtney Maligi,Shalini Dalal, Syed M.A. Naqvi, Diane Liu, and Eduardo Bruera Personalized Pain Goal as an Outcome Measure in Routine Cancer Pain Assessment. J Pain Symptom Manage 2018; 56: 80-87.
3)David Hui, Eduardo Bruera: A Personalized Approach to Assessing and Managing Pain in Patients With Cancer J Clin Oncol 2014; 32: 1640-1646
4)Yuki Sumazaki Watanabe, Tomofumi Miura, Ayumi Okizaki, Keita Tagami, Yoshihisa Matsumoto, Maiko Fujimori, Tatsuya Morita, Hiroya Kinoshita. Comparison of Indicators for Achievement of Pain Control With a Personalized Pain Goal in a Comprehensive Cancer Center. J Pain Symptom Manage 2018; 55: 1159e1164.
5)遺族によるホスピス・緩和ケアの質の評価に関する研究4(J-Hope4)
三浦 智史 遺族の考える症状緩和の治療目標(Personalized Symptom Goal) に関する調査(2025年6月10日 アクセス)
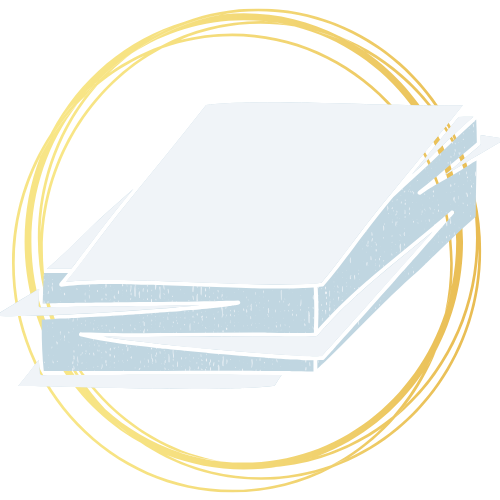

コメント